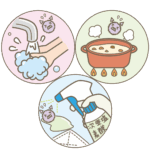水分をとろう!〜ペットボトル症候群に注意〜
夏本番。北海道でも観測史上1位を更新するほどの記録的な暑さです。
水分をしっかりとるようにと聞きますが、さて水分を摂らなきゃと思ったその時、あなたが手に取る飲み物は一体なんですか?
今回は、水分の摂り方と注意したい飲み物の選び方についてまとめました。
◯どれくらい水分をとればいいの?
成人の場合、体重の約60%は水分です。
割合は加齢とともに低下していき、高齢者は50%に減少しますが、それでも身体の半分は水ということになります。
ですが、その大事な水分は、汗や尿、便で身体の外に出ていってしまいます。その量は成人の場合、尿として約1300ml(1000〜1500ml)、汗や呼気などの私たちが意識しないうちに失われる水分(不感蒸泄)として約900ml、便から約100mlの合計約2300mlです。
一方、身体に入る水分には、飲料や食品から得られる水分や、身体のなかで生じる水分(代謝水)があります。
成人の場合、飲料から約1200ml、食品から約800ml、代謝水が約300mlで合計約2300ml/日となります。
水の出入りはこのようにバランスがとれているのが理想的です。
よく1日2L飲みましょうなどと聞きますが、これは少し曲解されていて、色々な経路から得られる水分全てで約2L/日を得られるといいですね。
では具体的にどれくらいが目安になるのか見ていきましょう。
▷年齢別の必要水分量の算出方法(1)
例えば、60歳55kgの方であれば、下記の式から
55(kg)×30(ml/kg/日)=1650(ml/日)となります。これは全ての経路の総計です。
体重(kg)×年齢別必要水分量=必要水分量
*年齢別必要水分量
25〜54歳 35ml/kg/日
55歳〜64歳 30ml/kg/日
65歳〜 25ml/kg/日
◯1.2L飲めますか?
ただ、ここから更に食事の中の水分量を差し引いて、飲み水の量を考えるのは現実的には難しいですよね。
熱中症環境保健マニュアル2022によると、1日1.2Lを飲み水としてとりましょうという目安が書いてあります。多いと感じてしまう人もいるかもしれません。
ですが、これはコップ1杯200mlとすれば6回ですから、朝昼晩のご飯の際に1杯ずつ飲めば3回、残り3回をどこかのタイミングで飲むことが出来れば達成です。あるいはもっと小分けにしてもよいでしょう。
おすすめは「トイレに行ったら水分もとる」をセットにすることです。立ち上がったついでにお水もとってみませんか。
またお風呂の前後でも飲むと、お風呂での脱水予防にもなりますね。
運動の有無や気温によって身体から出ていく水分量は変化するので、特に運動するときや暑い日にはいつも以上に意識して水分をとってくださいね。
◯清涼飲料水の糖分に注意
水分を摂らなくてはといっても、甘い飲み物ばかりを飲んでいると、別の病気になる危険性もあります。
それは、いわゆる「ペットボトル症候群」。
身体が処理しきれないほど大量の糖分が継続して身体の中に入ると、インスリンの働きが悪くなることで、糖分からエネルギーを得ることができなくなり、脂肪を分解してエネルギーを得る経路にかわります。その際にできる物質をケトン体といい、これが非常に多くなったときに様々な症状が起こります。
症状は、倦怠感、喉の乾き、多尿、食欲不振などがあり、重症化すると意識不明になることもあります。
だるく喉が渇くため、水をとろうとして、糖分を多く含む清涼飲料水を飲むと悪循環になってしまうのです。
清涼飲料水にどれくらい糖分が含まれているのかというと、平均10%程度の糖質が含まれているので、500mlのペットボトルでは50gの糖質が含まれている計算になります。これは1個4gの角砂糖が12.5個分ですから、とても多いことがわかりますね。(2)
清涼飲料水だけではなく、お水やお茶など糖分が含まれていない飲み物を多くとるようにしましょう。
◯経口補水液って毎日飲んでいいの?
ところで、脱水予防だったらよくCMで見る経口補水液ってやつを飲めばいいんじゃないの?と思う方もいらっしゃるかもしれません。
でも実は、予防のために飲むことはできないのです。
既に脱水を起こしている人に向けた成分の調整をしているため、毎日飲むには向いていません。
特にナトリウムやカリウムといった電解質が多く含まれており、例えばOS-1のペットボトル500ml1本には味噌汁1杯分のナトリウム、バナナ1本分のカリウムが入っています。(3)
高血圧や腎臓病などをお持ちの方、病院で食事指導を受けているような方は特に注意が必要です。
あくまでも病者用食品なので、日頃の脱水「予防」には水やお茶など別の飲み物を選んでくださいね。
経口補水液は下痢や嘔吐、発熱による脱水、脱水を伴う熱中症などの症状がある際に効果を発揮してくれますよ。
しっかり水分をとって、暑い夏を健康に乗り切っていきましょう!
参考
(1)明治 経腸栄養の基礎シリーズ① 投与エネルギー・水分量をどう決める?
(2)全国協会けんぽ 福井支部 「ペットボトル症候群」をご存知ですか
(3)経口補水液OS-1 高血圧、腎臓病、糖尿病等の疾患のある方でも飲めますか?
カテゴリー:ブログ